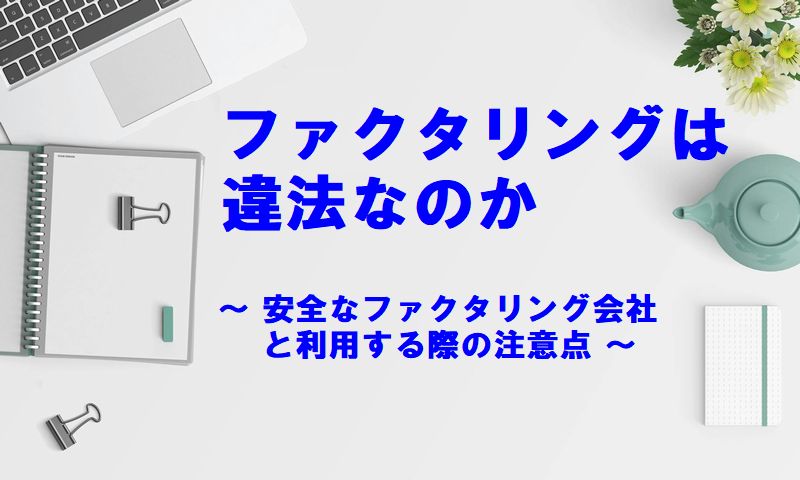ファクタリングは違法なのか⁉
安全なファクタリング会社と利用する際の注意点
ファクタリングを利用する際に気になるのが違法性です。違法なファクタリングを避けるためにも、基礎知識を押さえておくことが重要です。
この記事では、違法なファクタリングの見分け方を解説し、ファクタリングの種類や利用時の注意点についてもご紹介します。
ファクタリングとは
一般的にファクタリングとは、企業などが資金調達のために行う取引方法の一つで、企業が保有している売掛債権(未回収の請求書など)を専門のファクタリング業者に売却し、代金を前もって受け取る仕組みです。この方法により、資金繰りを改善したり、即時の現金が必要な場合に利用されます。
例えば、取引先に商品やサービスを提供したが、その請求書の支払いが数か月先だった場合でも、その請求書をファクタリング業者に売却することで、すぐに現金を得ることができるサービス全般を指します。
ファクタリングの語源となる英語の “factoring” は、もともと「計算の因数分解」などの意味を持つ言葉ですが、商業や金融分野においては「分解して利用する」という概念に転用されました。具体的には、企業の売掛債権を「要素」(因子)として取り出し、それを買い取って資金調達に活用する仕組みが生まれたという訳です。つまり、「ファクタリング」は取引の複雑な要素を整理して資金化するところからこの言葉が使われるようになったと考えられています。
ファクタリングの合法性と誤解されやすいポイントを解説
ファクタリングを利用するにあたり、その法的な正当性に不安を感じている方もいるかもしれません。しかし、結論から申し上げると、事業者向けのファクタリングは法律に基づいた正当な取引であるばかりか、ファクタリングを適切に活用すれば、その効果を最大限に引き出し、事業の成長をサポートする強力な手段となります。
ただし、現在のところ、ファクタリング業務を詳細に規定する専門の法律は存在せず、消費者金融における貸金業法のような明確な枠組みは確立されていません。そのため、取引の実態によっては法的な解釈が分かれるケースがあり、一部の行為が違法と見なされる可能性もあります。
ファクタリングそのものは適法である一方で、契約内容によっては貸付行為と見なされてしまい運営会社の形態によっては違法性が生じるリスクがあるという点を理解しておくことが不可欠です。利用する際には、どのような取引が問題になり得るのかを十分に把握したうえで、ファクタリング会社選びは慎重に検討する必要があります。
本記事では、ファクタリングが「違法」と誤解される背景や関係法令の解釈、さらにどのようなケースで問題視されやすいのかを詳しく解説していきます。
ファクタリングの法的基盤と留意点
ファクタリングは企業が資金調達をするための一つの方法で、売掛債権をファクタリング会社に譲渡し、現金化する仕組みです。この業務は民法で定められた「債権譲渡契約」に基づいて行われるため、通常は貸金業法の対象外となります。そのため、貸金業のような登録や許認可を取得する必要は基本的にありません。
ただし、いくつかの例外があります。「償還請求権付きファクタリング」や「給与ファクタリング」などの特定の形態では貸金業としての登録が必要になる場合があります。また、信頼性を向上させるために貸金業登録を検討するのも一つの方法です。
また、適切なファクタリングサービスを選ぶことは非常に重要です。契約内容を十分に確認し、法的な基盤や手数料の妥当性を検証して、リスクを最小限に抑えることが求められます。信頼性のある業者を選ぶ際は、契約書の内容や会社情報をしっかりチェックすることが肝心です。ファクタリングが事業成長の強力な手段となるよう、賢く利用するのがポイントです。
ファクタリングが法律上の問題として指摘されるパターン
ファクタリングが法的に問題視される際に、特に関係があるとされるのが、以下の3つの法律です。ここでは、これらの法律がどのようにファクタリングと関連し、なぜ違法と誤解されるのか、そして適法性の根拠について詳しく解説していきます。
- 弁護士法
- 利息制限法
- 貸金業法
弁護士法
ファクタリングと弁護士法の関係――違法と誤解される理由とは?
ファクタリングは、弁護士法に抵触する可能性があるのではないかと疑問視されることがあります。その理由として挙げられるのが、弁護士法第72条および第73条の規定です。
弁護士法第72条では、弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱ったり、その周旋を行うことを禁じています。これには、債権者の代理交渉や催告、裁判書類の作成などが含まれます。
弁護士法第73条では、弁護士以外の者が、他人の権利を譲り受けた上で訴訟や調停、和解といった手段を用いて回収を行うことを禁止しています。
この規定に照らすと、ファクタリング業者が債権を譲り受け、回収を行う行為は弁護士法違反ではないかと疑われることがあるのです。
サービサー法による合法性の明確化
しかし、こうした疑念を解消するために制定されたのが、「債権管理回収業に関する特別措置法(通称:サービサー法)」です。この法律により、国の許可を受けたサービサー(債権回収会社)は、特定金銭債権に限り、弁護士でなくても債権回収を営利目的で行うことが可能となりました。
また同法において、ファクタリング業者が業務として買い取った債権も「特定金銭債権」として認められたため、「自らが保有する債権を回収する行為」は弁護士法72条には抵触しないと明確化されたのです。
ファクタリング業者の運営基盤の強化
さらに、ファクタリング業者が依頼者から買い取った債権が回収困難に陥った場合でも、特定金銭債権に該当する債権であれば、サービサーに回収を委託することが可能となりました。これにより、ファクタリング業者の運営の安定性が向上し、業界の信頼性も高まっています。
「特定金銭債権」であるための要件とは?
ただし、すべてのファクタリング取引が特定金銭債権に該当するわけではありません。特定金銭債権として認められるためには、法律上明確な定義はありませんが、実務上は、ファクタリング業者が売掛債権のリスクを負う(ノンリコース型)場合に該当すると解釈されます。
これに対し、業者が債務者に対して求償権を持つ(リコース型)場合は、実質的に貸付と見なされ、貸金業法違反に問われるリスクがあるため、適切なファクタリング業者を選ぶことが極めて重要です。
ファクタリングは、債権のデフォルトリスクを業者が負担するノンリコース型であるからこそ、特定金銭債権として扱われ、弁護士法違反に該当しないと考えられます。適法なファクタリングを利用するためには、業者の仕組みや契約内容を十分に理解し、慎重に選択することが求められます。
利息制限法
ファクタリングは利用の際に発生する手数料の割合に関して、利息制限法で定められた利息上限に違反しているのではないか?と指摘される場合があります。
実際にファクタリングの手数料は以下の利息制限法の上限金利を大きく上回ったように見える場合もあるからです。
しかし、まず前提として押さえておきたいのは、ファクタリングには金利が存在しないという点です。なぜなら、ファクタリングは「融資」ではなく、「債権譲渡」に分類される取引だからです。そのため、利息制限法などの金利を規定する法律の適用範囲外となります。
とはいえ、取引にかかる手数料と取引終了までに時間で計算上の年率金利を計算することで、ファクタリング手数料の実態を年率で評価することが可能となります。以下の手法で簡単に換算を行います。
手数料の年率換算方法
- 現金化された日と本来の入金日の差 = aヶ月
- ファクタリング手数料 = b%
→ 月利 = b ÷ a → 年利 = 月利 × 12
例えば、支払いサイト2ヶ月の売掛債権を発生直後に現金化する場合、a = 2として計算します。
具体例: 2社間ファクタリング
- 手数料10%(低い手数料の場合) 年率換算 = (10% ÷ 2ヶ月) × 12ヶ月 = 60%
- 手数料20%(一般的な手数料の場合) 年率換算 = (20% ÷ 2ヶ月) × 12ヶ月 = 120%
- 手数料30%(高い手数料の場合) 年率換算 = (30% ÷ 2ヶ月) × 12ヶ月 = 180%
ファクタリング手数料が10%の場合、支払いサイト2ヶ月で年率換算が60%に達することがあり、これは利息制限法の上限金利(年率15%~20%)を大幅に超えます。
ファクタリングは、売掛債権を売却する仕組みであり、従って借入には該当しないため、利息制限法の適用対象外となります。
その条件として、債務者の財務状況が悪化して債権を回収できなくなった場合でも、発生する損失をすべてファクタリング会社が負担する点があります。
ファクタリング会社が未回収リスクを全面的に負う場合に限り、売掛債権の譲渡として認められ、利息制限法の上限を超える手数料を設定しても合法となるのです。つまり、債務者の支払い不能による回収不能リスクをファクタリング会社が完全に引き受けることにより、この取引は特定金銭債権と見なされ、弁護士法の規制を受けることもなく、また貸金業でもないため利息制限法にも違反しません。
貸金業法に抵触する場合
ファクタリングは原則として「債権譲渡契約」に基づいて行われるため、貸金業法の規制対象ではありません。ただし、以下のケースでは貸金業法に抵触する可能性があります:
- 償還請求権付きファクタリング:売却した債権が回収できなかった場合、ファクタリング会社が利用者にその補填を求める権利(償還請求権)がある場合、これは形式的に「貸付け」とみなされる可能性があります。その結果、貸金業法の対象となります。
- 利息制限法の違反:ファクタリング手数料が実質的な「利息」と見なされた場合、利息制限法に違反する可能性があります。過度な手数料は注意が必要です。
抵触を避けるための注意点
ファクタリングを合法的に行うには、契約書で償還請求権がないことを明確に記載し、債権譲渡契約であることを明示する必要があります。このポイントが、取引の適法性を守る鍵です。
ファクタリングの根拠となる法律は民法のみ
ファクタリングの法的根拠について詳しく解説していきます。ファクタリングは「債権管理回収業に関する特別措置法」によって業務の合法性が明文化されましたが、ファクタリング業には、銀行法や貸金業法のような明確な「業法」が存在しません。そのため、主に 民法や会社法、金融関連の法律(場合によっては出資法や貸金業法の適用リスク) に基づいて運営されています。
規制がほとんどないのでどんな業者でも参入することができる一方、守ってくれる法律がないので違法な業者に注意しなければなりません。
ファクタリング行為の根拠となる民法上の条項は、主に以下の規定に基づいています。
- ファクタリングの民法上の根拠
ファクタリングとは、売掛債権を譲渡し、資金調達を行う取引のことです。その根拠となる民法の規定は以下の通りです。
- 民法第555条(売買)
売掛債権の譲渡が金銭との交換で行われるため、売買契約として位置付けられる。 - 民法第466条(債権の譲渡性)
債権は法律や契約で禁止されていない限り譲渡できる。 - 民法第467条(債権譲渡の対抗要件)
債権譲渡を第三者に対抗するためには、通知または承諾が必要。
- 2社間ファクタリングの民法上の根拠
概要:売掛先(債務者)には通知せず、売掛債権をファクタリング会社に譲渡する方式。
根拠条文:
- 民法第555条(売買):売掛債権の売却に関する規定
- 民法第466条(債権譲渡の自由):債権を譲渡できる原則
- 民法第468条(指名債権の準占有者に対する弁済):売掛先が元の債権者に支払った場合、一定条件下で有効とみなされる
→ 2社間ファクタリングでは、売掛先が債権譲渡を知らないため、元の債権者に支払った場合のリスクがある。
- 3社間ファクタリングの民法上の根拠
概要:売掛先(債務者)に債権譲渡を通知し、ファクタリング会社に直接支払わせる方式。
根拠条文:
- 民法第555条(売買):売掛債権の売却に関する規定
- 民法第466条(債権譲渡の自由):債権譲渡が原則自由であること
- 民法第467条(債権譲渡の対抗要件):債務者への通知があれば、第三者に対抗できる
→ 3社間ファクタリングでは、通知が行われるため、債権譲渡の効力が確実となる。
| ファクタリング種類 | 債権譲渡の通知 | 主な根拠条文 | 特徴・リスク |
| 2社間ファクタリング | なし | 民法466条 468条 |
売掛先に通知せず、迅速な資金調達が 可能だが、二重払いリスクがある |
| 3社間ファクタリング | あり | 民法466条 467条 |
債務者に通知するため、リスクが 低いが、手続きに時間がかかる |
それぞれの方式にはメリット・デメリットがあるため、状況に応じて選択することが重要です。
詳細な法律がないので違法な業者に注意
このように、ファクタリングの法的根拠は民法の債権譲渡と売買契約が主になります。
そのため、営業をするために国などへ登録や許認可をする必要もなく、どのような事業者でも突然ファクタリング事業を行うことが可能なのです。
ファクタリングの手数料は法的に上限や一定の基準が定められているわけではないので、業者によって手数料が大きく異なることもあります。ファクタリング業者の中には明らかに高すぎる手数料を設定する違法な業者も存在しますので、くれぐれも業者選びには注意しましょう。
結論
債権の売買を基にしており、融資ではなく「債権譲渡」に該当するため金融庁への登録は不要です。
貸金業とみなされる場合
以下の条件に該当する場合は貸金業として届け出が必要となります。
- 償還請求権付き:売掛金が回収不能の場合に利用者が買い戻す義務を負う場合。
- 利用者の信用審査のみを行い、売掛債権の調査をせずに資金提供した場合。
- 債権実態がなく単なる資金提供の場合。
- 金融庁の監督を受けるケースとしては、銀行や貸金業者によるファクタリング、証券化や金融商品の一環として行うファクタリングが該当します。
| 項目 | 金融庁への届け出 登録 |
備考 |
| 通常のファクタリング業者 | 不要 | 債権の売買は貸金業ではないため |
| リコース(償還請求権)付きファクタリング | 必要 | 貸金業とみなされるリスク |
| 利用者の信用のみで資金提供する場合 | 必要 | 実質的な貸付と判断される可能性 |
| 銀行・貸金業者が行うファクタリング | 必要 | 銀行法・貸金業法の適用 |
| 証券化・投資商品としてのファクタリング | 場合による | 金融商品取引法の規制対象になる可能性 |
必見!安全なファクタリングサービスの見分け方
- 契約内容を確認する
- 契約書に「売掛債権の売買(債権譲渡契約)」の記載があるか確認。
- 記載がない場合、高金利貸付けの可能性あり。
- 契約書を保管してトラブル防止しましょう。
- 会社情報をチェックする
- 住所や電話番号が実在するか確認。
- 架空の住所や携帯電話のみの業者は避ける。
- 手数料を相場と比較する
- 2社間:10~20%、3社間:1~9%が相場。
- 相場を大きく超える業者は注意。
- 担保や保証人の記載を確認
- ファクタリング契約に担保や保証人の記載があれば違法の可能性。
- 償還請求権の有無を確認する
- 償還請求権(リコース)がある場合は、貸金業法の規制対象となり業者に貸金業の届け出が必要となる。
- 支払いは一括であるか
- 一括払い以外(分割払い)を認める業者は違法のリスクある。
違法業者対策として違法な特徴を知り、信頼できる業者を選ぶことが重要です。利用前に十分なチェックを行いましょう!
事前に見積もりを請求することが有効です!
複数のファクタリング業者に事前の見積書を請求することは、優良業者を見極めるうえで非常に有効な手段となります。見積もりを通じて、手数料や手取り金額を具体的に把握でき他の業者と比較することで、不当な条件を回避できます。
- 契約内容の確認 契約前に詳細を確認することで、後々のトラブルを防止できます。特に担保や保証人の記載がないか、償還請求権の有無をチェックすることが重要です。
- 信頼できる業者の選定 複数の見積もりを比較することで、信頼性の高い業者を選ぶことができます。住所や電話番号が実在するかも確認しておきましょう。
まとめ
ファクタリングは、適切に利用すれば資金調達の強力な手段となります。しかし、その仕組みや法的基盤を正しく理解しないと、違法業者に巻き込まれるリスクもあります。特に、弁護士法・利息制限法・貸金業法に抵触しない正規の取引であるかを見極めることが重要です。
安全なサービスを選ぶためには、事前に契約内容を確認し、適正な手数料かどうかを見積もりで比較することが有効です。ファクタリングの根拠は民法にあるものの、詳細な法律が整備されていないため、信頼できる業者選びが不可欠です。ルールを理解し、正しい知識を持つことで、リスクを回避しながら賢く活用しましょう。
信頼できるおすすめ ファクタリング会社
| 会社名 | ビートレーディング | JTCの入金前払いシステム | QuQuMo(ククモ) | 三共サービスのファクタリング | フリーナンス【FREENANCE】 | 日本中小企業金融サポート機構 | 会社名 | |||
| 早急な資金繰りが必要な場合 | 早急な資金繰りが必要な場合 | |||||||||
| 手数料を重視する場合 | 手数料を重視する場合 | |||||||||
| 審査通過率の高さを重視する場合 | 審査通過率の高さを重視する場合 | |||||||||
| 秘匿性を重視する場合 | 秘匿性を重視する場合 | |||||||||
| 手続きの簡便さを重視する場合 | 手続きの簡便さを重視する場合 | |||||||||
| フリーランス向け | フリーランス向け | |||||||||
| 公式ホームページ |  |  |  | 公式ホームページ | ||||||
| 詳しく見る | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳細 | 詳しく見る |